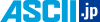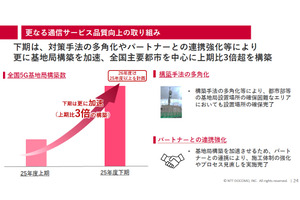NTTドコモは、高度20kmの成層圏を飛行する無人航空機(HAPS)を用いた、地上のスマートフォンへのデータ通信の実証実験を今年2月に成功。
MWC Barcelona 2025の同社ブースでもHAPSに関して展示が見られる。そこで2026年の商用化に向けて開発を加速させるという、ドコモのHAPS戦略について、同社コーポレートエバンジェリストの中村武宏氏に話を聞いた。
上空20kmで飛び続ける無人飛行機で半径50kmの範囲をエリア化
災害時の通信手段としても期待が持たれている
HAPS(High-Altitude Platform Station)は、成層圏に滞留する無人航空機のこと。地上基地局の代替として機能し、広範囲な通信エリアを効率的にカバーが可能。従来の基地局設置が困難な場所や、災害時の通信手段として、その活用が強く期待されている。
HAPSの主な利点について、中村氏は「広範囲なエリアカバー」と「柔軟な配置」、そして「災害に強い」点を挙げる。
エリアについては、1機あたりで半径50kmをカバーすることが可能で、成層圏を飛行し、必要な場所に柔軟に配置できるため、カバレッジが手薄な地域にも対応しやすい。さらに地上のインフラがダウンしてしまったケースでも、HAPSが自律的に通信を確保してくれるわけだ。
今回のケニアでの実証実験では、Space Compass(NTTとスカパーJSATのジョイントベンチャー)との共同で実施。この実験では、AALTOが製造および運用する小型固定翼型のHAPS機体「Zephyr」を使用し、高度約20kmの成層圏を飛行させている。さらに地上のLTE基地局からの電波をHAPSで中継し、地上のスマートフォンとのデータ通信に成功しているとのこと。
中村氏は「今回の実験では、サービスリンクに2GHz帯(帯域幅10MHz)、フィーダリンクに38~39.5GHz帯(帯域幅10MHz)を使用しました。また地上ゲートウェイ局からHAPSを中継したスマートフォンへの通信(フォワードリンク)で4.66Mbps以上のスループットを記録し、HAPSから折り返される電波がスマートフォンで正常に受信できることを確認する実験をしています」とのこと。
「そのために実装したのが、HAPS機体から一定のエリアに通信カバレッジを形成するために地上の定点にビームの中心を向ける技術」と今回の実験について話すとともに、HAPSを介したスマートフォンへの直接通信が技術的に可能であることを証明できたとする。
まだまだ課題は山積しているものの
2026年に向けた商用化を進めている最中
この実証実験を踏まえ、NTTドコモは2026年内のHAPS商用化を目指しているが、初期段階では法人向けサービスが中心になりそうだ。
商用化に向けた課題については、「法整備、運用体制、コスト、安全対策など、さまざまあります。電波法や航空法など、関連する法規制への対応、機体の管理、運用、緊急時の対応など、包括的な運用体制の確立。HAPSの製造・運用コストの削減、他の航空機との衝突回避や、万が一の機体落下に備えた安全対策など課題は山積しています」と、正直なところまだまだハードルは多そうだ。
ただし、これらの課題に対し、NTTドコモは総務省や国土交通省との協議を進め、制度整備に向けた働きかけを進めていると同時に、同じくHAPSを推進するソフトバンクやSpace Compassといったパートナー企業との連携も強化し、技術開発や運用ノウハウの蓄積を図っている。
NTTドコモによるHAPSへの取り組みは、通信品質の大幅な向上だけでなく、災害に強い社会の実現、そして新たなビジネスチャンスの創出に繋がる可能性を秘めている。2026年の商用化に向けて、技術開発や法整備といった課題を乗り越え、空の基地局が実現する未来社会に期待したいところだ。