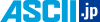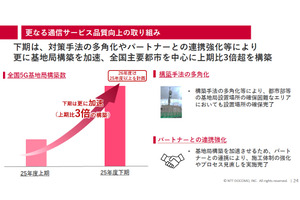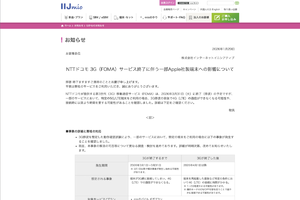ソフトバンクは17日、報道向けに「ソフトバンクが取り組む次世代コンピューティング研究に関する説明会」を開催した。
ソフトバンクには、新しい技術を社会実装するための研究・開発を担う「先端技術研究所」という組織がある。昨年発表されたAI-RANの総合ソリューション「AITRAS」や、自動運転、HAPS、量子コンピューターなど、近い将来の社会実装をめざし、多様な技術が研究されている。しかし、今回説明されたのは、実用化は「40~50年後になるかも」という時代をかなり先取りした“超先進的”な研究だ。
未来のコンピューターとして“脳”に着目
ソフトバンクが東京大学 生産技術研究所の池内与志穂 准教授と共同で研究を進めているのが「BPU」というもの。「Brain Processing Unit」の略で、脳細胞をコンピューターとして活用しようというものだ。
BPUには「脳オルガノイド」を用いる。脳オルガノイドとは、脳を模したもので、iPS細胞で培養した神経細胞が用いられている。大きさは0.5~1cm程度。脳オルガノイドに電気刺激を与えることで活動電位を取得できる。つまり、刺激を変化させることで活動をコントロールできるわけだ。
次世代のコンピューターとして、脳オルガノイドに着目したことについて、ソフトバンク先端研究所の朝倉慶介氏は、圧倒的に消費電力が少ないことと学習効率の高さを挙げた。人間は数少ない経験でも学習することができ、経験から瞬時に推測することもできる。
既存のコンピューターでは莫大な計算を要することも、脳の特性を活かせば効率よく計算できる、という仮説に基づいて研究されている。
脳オルガノイドに電気刺激を与えて学習させる実験に成功
脳は神経細胞のつながりの変化によって学習する仕組みだという。この変化をコントロールできれば、脳オルガノイドに学習させることができるわけだ。
まず、学習の基礎検証として、脳オルガノイドに異なる電気刺激を与えて、活動の変化を計測する実験が行なわれた。具体的には、1分間に1回の電気刺激を与え、それを30回続ける。1つは刺激と刺激の間に何もしない。2つ目は刺激の間にも一定の弱い刺激を与え続ける。そして、3つ目は刺激の間にランダムなノイズを刺激として与え続けて、活動を比較した。
その結果、一定のパターンで刺激を与えると特徴的な活動が生じ、ランダムなノイズを与えると、それを嫌がるかのように活動量が低下することがわかったという。
その結果をもとに、簡単なゲームにおいて、成功した場合と失敗した場合の刺激を変えて、学習させる実験も実施。20分の学習で成功率が1.5倍になるという結果が得られたという。
脳オルガノイドを結合させることで学習精度が向上
説明会には東京大学の池内与志穂 准教授も登壇。池内氏によると、脳にはいろいろな部位があり、それぞれ異なる役割を果たしているとのこと。脳オルガノイドは、脳全体を模したものではなく、ごく一部であり、いろいろな脳オルガノイドが作られているのが現状。
BPUの開発に向けては、複数の脳オルガノイドを結合させて、より高度な情報処理を実現する必要があるという。そこで、神経細胞から伸びる「軸索」という突起で複数の脳オルガノイドを連結する実験も実施。複数の脳オルガノイドを結合させた「コネクトイド」を用いることで学習精度が高まることも確認できたという。
未来を先取りできるイベントも開催
ソフトバンク先端技術研究所の杉村聡太氏は、現在の脳オルガノイドを人に例えると「生まれたての赤ちゃんのようなもの」と言う。しかし、人間の成長と同じように、今後の研究によって人工知能を高度化することを期待できるようだ。社会実装はかなり先になるが、研究の過程で得られた知見や技術を活かすことも想定されている。
2月1~9日にはイベント「ソフトバンク × 真鍋大度 × 東京大学 特別展 Brain Processing Unit -生命とコンピューターが融合する未来-」が開催される。真鍋大度氏は、脳オルガノイドの研究に参加し、それを用いた作品を制作しているアーティストだ。
BPUは2022年から研究されているが、ソフトバンク先端研究所の朝倉慶介氏は「まだ実現する可能性があることがわかった段階。正直、まだどうなるのかはわからない」と言う。しかし、イベント開催の意図について「将来に向けたビジョンを発表することで、ワクワクするような期待感を持っていただきたい」とも話していた。
イベントの詳細は下記サイトを確認できる。事前予約が必要なので、興味のある人はお早めに!