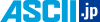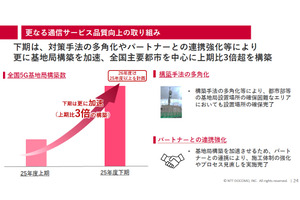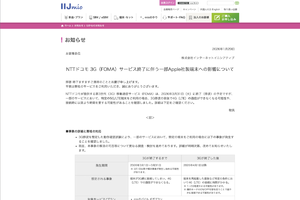グーグルの最新スマートフォン「Pixel 10」シリーズが発表された。その中でも上位モデルに位置する「Pixel 10 Pro」は、ディスプレーが6.3型と現在ではコンパクトなサイズ感ながら、最大100倍ズームな望遠カメラを備え、なおかつグーグル独自開発の最新チップセット「Tensor G5」によるAI関連機能が大幅に強化され、本格的なAIスマートフォンへと進化している。
発売前の実機からその中身を確認してみよう。
見た目は「Pixel 9 Pro」に酷似
唯一の見分け方は?
まずは外観を確認すると、ディスプレーサイズは先にも触れた通り6.3型で、サイズは約72×152.8×8.6mm、重量は約207gと、前機種の「Pixel 9 Pro」と比べるとサイズに大きな違いはないが、重量は10g弱ほど重くなっている。
一方、デザイン面はPixel 9 Proと大きな違いはないようで、「Pixel 9」シリーズから採用された、グーグルの検索ボックスを意識したとされる、丸みのある横長のカメラバーデザインを継続。それゆえカメラ部分のバンプ(出っ張り)もかなり大きく、ケースを装着せずに使う際には出っ張りによる引っ掛かりに注意が必要。
背面素材もPixel 9 Proと同様、マット調のガラス素材を採用しており、右側面に電源キーと音量キー、底面にUSB Type-C端子が備わっている点も共通している。それゆえ実は、両機種を見た目だけで見分けるのはかなり難しい。
そこで注目したいのがSIMスロットだ。なぜなら、Pixel 9 ProのSIMスロットは本体底面に配置されていたのに対し、Pixel 10 ProのSIMスロットは上部に移動しているからだ。Pixel 9 ProかPixel 10 Proかを見た目で判断するには、まずSIMスロットの位置を確かめるのがいいだろう。
そしてもう1つ、見た目には分からないが大きく変化しているのが「Pixelsnap」である。これは背面のワイヤレス充電に「Qi2」の規格を採用したもので、アップルのiPhoneシリーズの多くで対応している「MagSafe」と同様、磁石でワイヤレス充電器を装着できるようになったのだ。
それゆえ、Pixelsnap対応の充電器を用意することで、ワイヤレス充電時の“ずれ”を気にする必要がなくなったのは、ユーザーとしてもうれしいポイントといえる。周辺機器は今後サードパーティーから順次発売されるとのことだが、筆者が確認した限りでは、既存のQi2に対応したマグネット付き充電器でも充電はできるようだ。
カメラ性能は据え置きも
AIと100倍ズームで強化
見た目には大きな変化がないPixel 10 Proだが、実はカメラの性能も大きく変わっていない。
Pixel 10 Proの背面カメラは、1/1.3型で5000万画素(F1.68)の広角カメラと、1/2.55型で4800万画素(F1.7)の超広角カメラ、1/2.55型で4800万画素(F2.8)かつ光学ズーム5倍相当の望遠カメラの3眼構成。フロントカメラは4200万画素(F2.2)で、スペックを見る限りPixel 9 Proと変化はない。
それゆえ撮影した写真の品質も、Pixel 9 Proと大きく変わるわけではないようだが、Pixelシリーズはカメラのハードウェア性能だけでなく、AI技術を積極的に取り入れて画質の強化を図ってきた経緯がある。それだけに、Pixel 10 ProもAIでカメラの強化を図っているようで、その1つが「超解像ズームPro」だ。
実はPixel 10 Proは、望遠カメラの性能自体は同じながらもデジタルズームが強化されており、Pixel 9 Proが最大30倍までだったのに対し、Pixel 10 Proは100倍までのデジタルズームが可能となっている。ただ、30倍超のデジタルズームはさすがに画質が落ちてしまうのだが、それをAI技術でクリアにするのが超解像ズームProである。
具体的には30倍以上のズームで撮影した写真に、生成AIの技術を取り入れ鮮明な写真にしてくれる。生成AIを用いるだけあって、元の被写体を完全に再現してくれるわけではないことと、正確性を期すため人物の顔には適用されないといった制約はあるが、かなり離れた場所にある被写体を鮮明にしてくれるのは驚きだ。
超解像ズームProは設定をオンにしておくと撮影後に自動で適用されるのだが、適用前後の写真のうちどちらを使用するかはユーザーが選べる。生成AIを用いるだけあって超解像ズームProによる補正でかえって写真が不自然になる場合もあるだけに、撮影後は好みに応じた写真を選ぶのがいいだろう。
そしてもう1つは、AIを活用したカメラ関連の新機能。AIが撮影のアドバイスしてくれる「カメラコーチ」だ。これはカメラアプリで撮影する際、カメラを被写体に向け、右上のカメラマークをタップすると利用できるもの。
カメラコーチを呼び出すと、AIが被写体をどのように撮影したいか、構図の候補を提示してくれる。それらのうち1つを選ぶと構図通りに撮影するため、被写体をフレームのどこに配置するか、カメラをどこに向けるかなど、さまざまな指示をしてくる。あとはその指示に従って撮影すれば、よりよい写真を撮影できる。
カメラコーチはAIが構図を判断するため、何度か試していると時には予想しない構図の指示が現れることもある。ただそれを逆手に取って、意外性のある写真を撮影するのに活用するのもいいだろう。