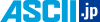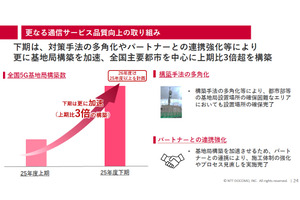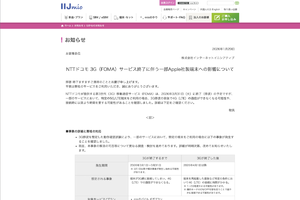9月20日にドイツ・ベルリンで「グランツーリスモ ワールドシリーズ2025」の第2戦「ラウンド2 - ベルリン」が開催された。グランツーリスモシリーズのプロデューサーであり、ポリフォニー・デジタルCEOの山内一典氏に、ビジョングランツーリスモプロジェクトの最新作であるオペルの「コルサ GS ビジョン グランツーリスモ」の発表や、GTシリーズが30年近くにわたり世界中のカーマニュファクチャラーと築いてきた関係、そして今後の展望について話を伺った。
未来へのヒントをゲームに込めるVision GTプロジェクト
今回、オペルとのコラボレーションにより発表された「コルサ GS ビジョン グランツーリスモ(Corsa GSE Vision GT)」について、山内氏はまず開発の背景を説明した。このプロジェクトは、オペル側から「ビジョン グランツーリスモの車を作りたい」という要望からスタート。山内氏は実際にオペルのデザインセンターを訪れ、そこに展示してあったオペルの過去の様々なコンセプトカーを見て感動を覚えたという。
ビジョングランツーリスモプロジェクトは数年前に「カーデザインのプロジェクト」として始まった。しかし、年月が経つにつれ単なるデザインの提示に留まらず「車の未来をこう考えるというプロジェクト」に変化しつつある。このコルサ GS ビジョングランツーリスモも、そのような位置付けの車であるのだ。
コルサという車はすごくポピュラーな車種で、オペルを代表する車でもあり、このようにポピュラーな車が将来どうなるのか、どのように風に進化していくのかというヒントが、コルサ GS ビジョン グランツーリスモに詰まっているとのこと。
マニュファクチャラー(メーカー)がビジョングランツーリスモのコンセプトカーを制作する際、ポリフォニー・デジタル側からは基本的に制限や制約は与えないと山内氏は説明する。
ゲームへの実装プロセスは、まずエクステリアとインテリアのデザインがマニュファクチャラーのデザインセンターで決めらるところから始まる。そのデザインを受け取り、ポリフォニー・デジタル側がモデリングし、実際にシミュレーターで走行テストをする。この際にマニュファクチャラーから受け取った車の詳細なデータを反映させることで、マニュファクチャラーが指定するスペックの車が完成するのである。
メカニズムに関しても、マニュファクチャラーが考えるさまざまなメカニズム、たとえばドライブトレインのあり方や、4つのタイヤのトルクベクタリングをどうするかといった部分は自由度が高く、その車のためだけに新しいメカニズムを実装することもよくあるとのこと。
さらにゲーム内で走らせた結果、たとえば「フロントの車高をもう20mm上げたい」といった改善点が見つかると、フィードバックを通じて車を煮詰めていくという、実車開発にも似たコミュニケーションが行なわれるとのこと。
「計算可能な存在にする」という30年継続の哲学
ビジョングランツーリスモプロジェクトが12年間にわたって続き、多くのメーカーが関心を示し続けることについて、山内氏は「1つのプロジェクトで、本当にたくさんのデザイナーやモデラー、エンジニアが関わっており、それを“やろう”と思ってくれるマニュファクチャラーが絶え間なく現れてくださっていることは、本当に光栄なこと」とその思いを強調した。
さて、グランツーリスモシリーズはまもなく30周年を迎える。山内氏に30年という長きにわたり開発を続けているモチベーションの源泉について尋ねると、「車が好き」という純粋な情熱と「車をリアルに再現したい」という終わりなき探求心、そして毎回新たなチャレンジに挑み、変化を続けてきたことだという。
デジタル空間内で車を再現するというこの取り組みは、終わりのない挑戦であり「もっと良くしたい」という探求心が絶えず湧き上がってくるのだと山内氏は語った。
またそれだけではなく、グランツーリスモに登場する1台1台の車は、それぞれに多数の人の情熱が詰まって生まれており、そういったパッションがグランツーリスモの中に込められてるからこそ、グランツーリスモはこの30年間続けて来られた理由だと山内氏は力説した。
長年続けてきたグランツーリスモのフィロソフィーはどのようなものなのだろうか。一言で表すのは難しいとしながらも、ポリフォニー・デジタルの創業以来の哲学として、山内氏は次の言葉を挙げた。
「この宇宙、この世界に存在するあらゆるものを計算可能な存在にする」。
つまり車やランドスケープを計算できる存在とすることで、デジタルゲームの根幹であるコンピューターを活用できるようになり、そこから最終的にドライビングシミュレーターを作り出すことが可能になるのである。
自動車産業が電動化へと向かう中で、グランツーリスモが持つ役割についても言及した。一部では電動車(EV)ではドライビングプレジャーが失われるのではないかという懸念の声があるものの、山内氏は自身のEVドライビング体験から、これまでの車同様のドライビングプレジャーがそこにはあると感じているとのこと。
そしてグランツーリスモに込める願いとして、グランツーリスモは常に本物のドライビングプレジャーを安全に学ぶためのツールとして使ってもらい、最終的には本物の車で、この大地を走るという経験をゴールにしてほしいとも述べた。
産業との共存とコミュニティーへの対応
グランツーリスモは常にカーマニュファクチャラーと込み入った議論を続けている。グランツーリスモを通して自動車産業がこの先どこの方向に向かっていくのか、あるいはどこでどう悩んでいるのかということも徐々に見えてくるようになっているという。
そもそもグランツーリスモには本物の車が登場することが一番の価値であり、そのためにも常に自動車産業との協業を考えていると山内氏は話した。グランツーリスモは自動車産業と足並みを揃えながら進化していく存在なのだ。
最後に、熱心なコミュニティーから寄せられる「なぜこの車が入っていないのか」といったフィードバックへの対応についても山内氏は触れた。
山内氏は「コミュニティーの声には常に耳を傾けている」と説明しながらも、グランツーリスモには30年にも及ぶ歴史があり、ジェネレーションや国によってカーカルチャーが異なるため、要望にすべて一斉に対応することはできないと説明。時間はかかるもののコミュニティーに対しては順番に対応していく予定とのことだ。