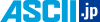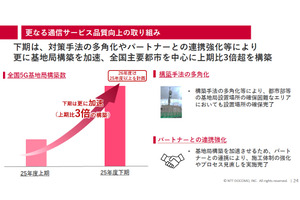AQUOS R10の魅力を知り尽くすための1日
スペックだけじゃ、語りきれないものがある──参加した人の誰もが、こう思ったはず。
シャープの最新スマートフォン「AQUOS R10」を主役にしたファンミーティングが、アスキー編集部とシャープの共催で開催された。
集まったのは、スマホ好きなインフルエンサーたちと、製品を“つくった人”。機能のこだわりを聞き、実際に触れて、開発者と語り合う。肩肘張らず、でも中身は濃い。そんな一日をのぞいてみよう。
イベントの舞台は、都内の角川アスキー総合研究所・本社。ファンミーティングは、まずプレゼンテーションのセッションからスタートした。
はじめにシャープ 通信事業本部 パーソナル通信事業部 回路開発部 部長の生野容正さんが登壇し、AQUOS R10の設計思想やディテールに込めたこだわりを語った。
生野さんによれば、AQUOS R10の設計上の特徴のひとつは“熱”の処理。年々高機能化が進むスマートフォンだが、性能の向上に伴って、プロセッサーを中心として基板から発生する熱をいかに処理するかは、メーカーの腕の見せどころとなっている。
AQUOS R10では、AQUOS R9に備わっていた放熱/排熱機構を進化させた、独自の熱処理技術を採用している。具体的には、熱伝導率の高い「銅ブロック」を新たに追加し、基板からの熱を受ける放熱グリスと、基板の電波干渉を防ぐ目的のシールドの素材を変更。さらにCPUとメモリの間のピンの隙間には、アンダーフィル(液状の硬化樹脂)を充填した。
これらの改良によって、基板から発生する熱をより効率的に排熱機構に伝え、速やかに放熱する設計が実現した。「効率的な排熱、放熱のために重要なのが、まず『伝熱』です」という生野さんの言葉が印象的だ。
シャープは、ユーザーからの意見を積極的に開発に反映していく姿勢を持っているメーカーでもある。特にAQUOS R10は「スマホが使用中に熱くなるのが困る」といったユーザーの声をSNSなどで頻繁に見かけたことも、開発に影響を与えたという。
「ユーザーの皆様から寄せられる意見を開発に活かしていくという姿勢は、いつも持っています。AQUOS R10は、ユーザーさんの声が開発に大きく関わったスマートフォンとも言えます。熱くなりにくく、重いゲームなどを快適に遊びやすいのも、AQUOS R10の魅力ですね」(生野さん)
AQUOS R10の「設計のこだわり」を生で体感!
会場内には、AQUOS R10の特徴を実際に試せる体験ブースも設けられた。
“カメラが強い”AQUOS R10の機能として注目したいのが、AIによる“影消し”機能。料理やテキストの写真を撮るときに、被写体にかかった影をAIが自動で補正し、周辺とうまく馴染ませて仕上げてくれるというものだ。試してみた参加者の多くが、「この機能があると、助かる」「自然な雰囲気で、加工っぽくならない」と盛り上がっていた。
さらに、AQUOS R10の分解モデルや、開発過程で使用する「カットモデル」などの展示も。
このカットモデルは、組み上げた完成品のスマートフォンにエポキシ樹脂を流し込み、いくつかの部位で切断することで、断面を見るために用いられる。
その意図は、「設計図通りに組み上がっているかどうかは、実際に組み上げてみないと確認できない(開発担当者)」から。断面を見ることで、設計図と同じように、部品が適切な場所に配置されているか/部品同士が干渉していないかといったことが検証できる。
筐体の剛性感の高さも、AQUOS R10の見どころのひとつ。アルミ合金のブロックを切削加工し、樹脂パーツと一体化させた、非常に精密な筐体を採用している。「プレスでは出せない、高い精度の加工ができる(開発担当者)」だけでなく、手に持った際の頑丈な手触りにも貢献している。